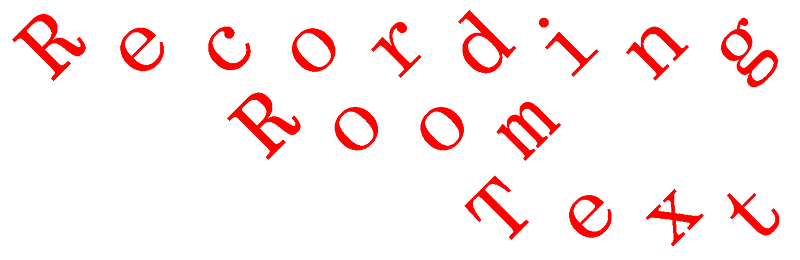楽譜
楽譜に書かれていること、書くことが出来なかったこと
木村知之
作曲家
プロローグ
私が曲を書く、つまり五線に⾳符を書く時何を考え書いているか、について最初に述べておこうと思う。作曲する、は英語では“Compose”と書くが、本来の意味は構成する、という意味である。つまり⼤半が思考する事で組み上がっていく。これは私だけではなく、恐らく作曲する⼈は⼤概思考によって作曲していると想像する。え!感覚で作るものじゃないの?と思われる⼈も多いかもしれない。しかし、作曲する上で感覚を使うのはせいぜいモチーフを思い浮かべる時くらいで、ほとんどは思考で構成される。その詳細を⾳符や様々な記号を使って、五線に書かれ楽譜が完成される。少なくとも私はそのように作曲している。そもそも思考で出来た曲で⼈は感動するのか?と思われるかもしれない。しかし、例えば壮⼤な教会を設計するにあたり、建築家がいちいち涙を流したり、打ちひしがれたりするのか?それと同様に作曲も綿密な計画と⼯夫、構想、構成、そして動機、インスピレーションによって完成する。本編では「思考により出来た楽譜がもたらすものとは?」を起点に、それが⾳楽へと⽣まれ変わる過程、また芸術とはなにかについて考えてみたい。
私が普段作曲し、書き終え、その楽譜を依頼者に⼿渡す時、いつも「この曲がどのように演奏されるだろう?」という期待と、そして不安に苛まれる。楽譜に書き込まれた情報は、⾃分が頭の中で鳴っている⾳の半分以下の情報しか書き⽰せていないように感じるからだ。その曲が直接奏者に具体的に説明出来た場合でも、それで全て伝わる訳ではなく、ましてや出版された楽譜だとさらにどうなるかわからない。つまり、全ては奏者に委ねることとなる。⼀⽅何かを伝える為の伝達⽅法である「⾔葉」は、保険会社の契約書や約款よろしく、誰がどのような⾒解で持って読んだとしても正確かつ齟齬なく伝えられることが出来る伝達⽅法である。「楽譜」は、そのような誰しもが具体的に理解しうる情報を提供する能⼒をもち備えていない。情報としては極めて曖昧な伝達メディアとして常々感じている。楽譜から発⽣した情報がどのようにして芸術へと昇華していくのか、次のような順番で展開していこうと思う。
1. 情報を伝えるという同じ機能を持つ「楽譜」と「⾔葉」の共通点と相違点
2. 「楽譜」に書かれた⾳符の裏に存在するものとは
3. 伝承⼝伝の強み
4. 楽譜と⾳楽の神秘という両輪のバランス
5. 芸術とは
1. 情報を伝えるという同じ機能を持つ「楽譜」と「⾔葉」の共通点と相違点
前述の保険会社の約款の例のように、⾔葉はそもそも伝えなければならない事柄を、具体的かつ明確に、時には数値化して記すことができるというポテンシャルがある。⼀⽅もう⼀つの機能として、ポエムのような詩的な表現も表すことができる。⾔わばユーティリティな側⾯を持っている。反⾯、楽譜は約款を具体的に表すことが出来ないことは容易に想像出来るだろう。そう考えると、「楽譜」はもっぱら何か具体的なものを表現するためのツールではなく、その⼈の⼼の中に移す写し出される潜在的景⾊であったり、匂いであったり、愛、悲しみ、喜びを表現するためのツールと⾔える。しかし楽譜⾃体がそれらの感情を表現できるわけではなく、演奏されて初めてその姿を現す。故に⾔葉はそれ⾃⾝で完全完結を⽬指せるのに対し、楽譜は半分またはそれ以上演奏家によって完成される。
楽譜の最終⽬的地である⾳楽は、⾮常にプリミティブな感情表現である。悲しい曲は、フレーズ、和⾳、リズム、⾳⾊、フレージングによって表現される。「声なく⽴ち尽くし、静かに絶望している男の姿」を⾃然な形で⾳楽は語る。⾳楽はそもそも⼈間の⼼の内を映し出すものであって、脳で考えた“思考”を表すには向いていないように思う。⼀⽅作曲する、また奏者が読譜をする⾏為は“思考”に多くを委ねられている。⾳楽を完成させるには、思考によって作曲された楽譜が、再び奏者の感情、潜在意識によって再構築されることで初めて完結する。故に、「楽譜がもたらすもの」とは、完成された⾳楽の半分、もしくはそれ以下に過ぎないと私は常に感じている。では、楽譜で現すことの出来ないものとは何か。
2. 「楽譜」に書かれた⾳符の裏に存在するものとは
楽譜は⾔うまでもなく、⾳の⾼さ、リズム、強弱、フレージング、アーティキュレーション、和⾳などが書かれている。これらはあくまで⼼の内を表現する⽬的で書かれているわけだが、この楽譜を⾒ただけで、「⼣焼けを⾒たときの感動」が伝わるのかといえば、それはそうとは限らない。その楽譜を⾒ただけでその曲の感動が読み取れるのは、おそらく⾳楽に熟練した⼈である。仮にその熟練した⼈が楽譜からの情報を得て、⼼の中で歌った場合、その⾳楽は、その⼈の内⾯的感情が反映されて、⼼の中で演奏されている。では、楽譜そのものの情報はあくまで無機質な情報を表しているに過ぎないのか。その例として、完璧に書かれた楽譜を、近年よく使われる浄書ソフトを使って無機質に⾳源として再⽣したとする。私の感覚からすると、およそ曲の30%から40%はその再⽣される⾳によって感じ取ることができると思う。ただ30% 40%である。残りの60% 70%は楽譜には存在していないということになる。楽譜には、出来る限り具体的な情報を記号を使って正確に書くが、感情や潜在意識の部分は落とし込めないのである。そうなると、やはり演奏する⼈の経験、テクニック、感情、潜在意識というものが反映されて、初めて100%の本来の⽬的である「⾳楽」になる。注⽬したいのは、楽譜に書ききれなかったその“余地”こそ⾮常に⾯⽩い。またなんとも神秘的な部分である。
3. 伝承⼝伝の強みについて
話は変わるが、私の職場は⾳楽⼤学であり、その授業のひとつに「アンサンブル」がある。その授業で、例えばフレーズやリズムを伝える際、私はなるべく⾔葉を使わずにその場で歌う、もしくは可能な限り弾いてみせる。なぜなら、そこで何か具体的なことを⾔葉にしてしまうと全てが壊れてしまうような気がするからである。もし私が詩の才能があり「秋の⼣暮れ、枯れた葉がひらり、⼒尽きた様に地⾯に落ちるように」のような表現がその場ですぐにできたら⾔葉もしばしば有効だ。しかし⾔葉で表現するよりも、⾳楽家は⾳で表現したほうがずっとニュアンスが伝わる筈。だからこそ私は歌い、弾くのである。
この⼝伝のような教授法について、ここで伝承⼝伝の強みに関する例を挙げたい。話は⾶躍するが、およそ2500年前仏教の開祖であるブッダがさまざまな説法をした。その内容は、即座にテキスト化されたわけではなく、約200年もの間、短い「詩」によって吟じられ(歌われ)後代に伝えられてきた。(最古の仏典の⼀つ「スッタニパータ」では、まさに短い詩句によって収められている)ところが、その後教えは経典としてテキスト化された。その結果として、元は⼀つの教えであった仏教も、今や何千という宗派に分裂した。後代の⾼僧たちが、その⼈物、国、⾵⼟、政治、また⼟着の宗教との交わり、さまざまな解釈が⽣まれ、さまざまな宗派が次々と⽣まれていったからである。私は、⼝伝として伝えられたものこそ恐らくブッダが説法したものに極めて近いものではないか、と考える。なぜなら吟じられた詩は加筆が極めて難しいからである。例を挙げると、⽇本古来の曲《さくら》を、⽇本⼈は楽譜を通じて知ったのでなく、歌い伝えられて知っている。この吟じられた唄を、果たして良いように改ざんや加筆できるだろうか?それはあまりあり得ないのでないか。何故ならその曲が、⽇本⼈のアイデンティティーに響き刻み込まれた感動があるからだ。そういうものには加筆アレンジする動機すらない。⼀⽅で先の仏典のように、テキストは加筆が可能である。テキスト⾃体はあくまで伝達するためのメディアであって、その⾼僧の解釈を容易に加筆可能である。余談だが、私が10年ほど前にインドのバラナシに⾏った時、現地で知り合った⽇本⼈の坊さんに、ガンジス川の辺りで10⼈くらいの少⼥が経典を吟じているビデオを滞在先のホテルで⾒せてもらった。それにはビデオの⾳声にも関わらず、ゾッとするような感動と神秘があった。次の早朝、早速それをこの⽬で⾒たいとガンジスに向かったが、残念ながら⾒ることが出来なかった。恐らく2400年前の仏教もこの様に伝えられていたのかと想像する。その神秘は、⾔葉で伝えられるより遥かに本能的であり、官能的で理由なく感動の淵へと誘う⽬に⾒えぬ⼒があった。
話を戻すと、⾳楽というものは感情、精神を現すための表現⽅法であるが故に、できる限り⼝伝であるべきだと考えるが、しかしかく⾔う私も「楽譜」という伝達法、メディアを使って作曲する。その理由は、先ほどの「スッタニパータ」に出てくるような、短い詩句の連続であれば⼝伝も可能だが、当然、長く複雑で膨⼤な情報を全て⼝頭で歌うには限りがある。またそれには直接赴く以外に⽅法はない。よって楽譜という伝達⽅法を取らざるを得ない。しかしそれらはネガティブな側⾯ばかりではない。寧ろポジティブな副作⽤として、演奏者が残りの半分を作りあげるという、⼤いなる余地を提供している。
4. 楽譜と⾳楽の神秘という両輪のバランスについて
これまで述べてきたように、楽譜というメディアが表現されているものに、演奏者が命を吹きむことで⾳楽は完成されるのだが、⾔い換えると、“思考”によりもたらされた楽譜と“感情または潜在意識”で表現される演奏、この両輪によって初めて完成するのが⾳楽であると⾔える。この思考と感情、理性と本能、⾔わば相反するものの共同作⽤によって⾳楽は⽣まれる。この「相反するものの共存」という⾔葉で思い出す⼤変興味深い⼀説をここで紹介したい。ヘルマン・ヘッセが書いた『知と愛』の中に次のような⼀⽂である。「そういう作品(退屈な)は最⾼のものへの願いを⽬指しながら、それを満たさないが故に、そういう作品には、神秘、という肝⼼なものが⽋けているが故に、ひどい幻滅を感じさすのであった。それはつまり、夢と最⾼の芸術品が共通に持っている神秘にほかならなかった」 また、「その神秘の本質は、~(中略)~ 他の場合には融和し難い世の中の最⼤の対⽴、すなわち出⽣と死、好意と残忍、⽣命と破壊とが、この形態の中では和解し共存するのである。」この⼀⽂は私に深い感動と感銘をもたらした。融和し難い世の中の最⼤の対⽴が、和解、そして共存している。これこそが⾳楽ではないか!と思った。
さて、⾳楽が完成するプロセスとして、思考による楽譜、また感情による演奏、この2つの両輪について触れたい。私が思うに最⾼の⾳楽に⽋かせないのは、この両輪のバランスと質にある。素晴らしい曲が楽譜として記されていても、演奏者が技量、また解釈や表現⼒等が劣っている、または感情が希薄であった場合、その⾳楽の値打ちは下がる事は容易に想像出来るだろう。その逆も然りである。つまりこの両輪のバランス、質が均等に配置され、初めて素晴らしい⾳楽として⽣まれるのである。芸術の素晴らしい所は先のヘッセの⼀節にもあるよう様に、正に、「相反するものがそこでは共存している」である。つまり、この芸術の究極の⽬的地は“調和”ではないか。
5. 芸術とは
芸術全般の源泉は、⽇々の⼈間の営み、⽣活、⾃然現象に深く根ざしている。一方、我々の生活に目を向けると、⽬に⾒えるもの、⼿に取る事ができるもの、また共通認識が可能な数字や価値に重きを置いているように感じる。とりわけヨーロッパにおける19世紀半ばの産業⾰命以降、その傾向は加速した。反対に⽬に⾒えないもの、また⼿に取ることが出来ないものの価値、精神的な何か、神秘的な何かは、値段と価値を数値化出来ないが故に蔑ろにされているように私には⾒える。しかし先の⾳楽の世界にもみられるように、真の調和とは、楽譜と演奏の例のように、両輪がバランスよく配置されてこそ素晴らしい芸術が⽣まれ、新たな神秘を⽣む。しかしこの神秘こそが現在最も下層に追いやられ、それどころか必要のないものに位置付けされているのではないかと危惧している。⼀⽅の⾞輪(⽬に⾒えるもの、数値化できるもの、認識できるもの)は⾮常に豪奢、⼀⽅の⾞輪(⽬に⾒えないもの、神秘的なもの)は⾮常に貧弱である、その⾞輪がガタゴトと歪みながら⾛っているのが今の世の中と⾔えるのではないか。
⾳楽とは。作曲家の思考と閃きによって楽譜と⾔う遺伝⼦を持った卵は、演奏家によって孵化し、命が吹き込まれ、⿃となり、演奏されることで意思を持ち、聴衆の⽿に届くことで⼤空へと⾃由に⽻ばたき、そして神秘の世界に溶け、やがて宇宙に帰っていく。その⾃然の循環こそが「調和された世界」である。楽譜はその世界の道標の役割を担っている。
本文=木村知之
注釈=玉田和平
木村知之
作曲家
演劇やミュージカル、モダンダンス、短編映画などに楽曲を提供。「スーパーリコーダーカルテット1・2」(共同音楽出版)作編曲担当。またベーシストとして、日野皓正、エディ・ヘンダーソン、オセロ・モリノー、村上ポンタ秀一など国内外の演奏家と共演。⼤阪芸術⼤学特任准教授、⼤阪⾳楽⼤学特任准教授。