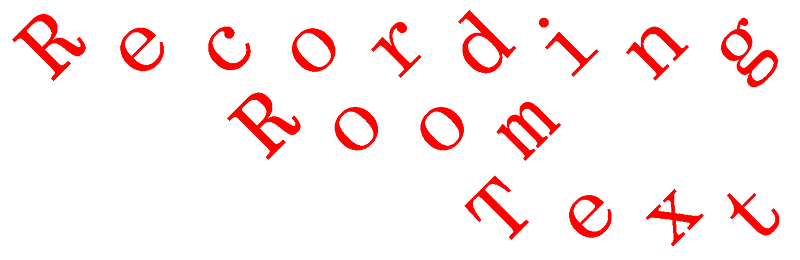メディア
メディアの不可能性を愛でること
舘かほる
写真研究者
メディアとは、ラテン語で「中間・媒介」などを意味する単語「メディウムmedium」の複数形であり、情報を媒介するものとして使われる言葉である。 例えば具体的な装置として、写真、映画、テレビ、そしてCDやカセットなどが挙げられる。また、「イタコ」などの霊媒術などもmediaの形態の一つである。写真や映像、音響の場合、かつてあった光や音の波長が、イタコであればもうこの世には居ない誰かのメッセージが内容となる。その目的は、いまここにないものをどこかから持ってくることである。
印画紙に映る母親の像、スクリーンに映るに揺れる肉の運動、ノイズの中でピアノの蓋が2回開け閉めされる音、死者のメッセージ。さまざまな形式で運ばれてきた情報は、そのなかに一つの独立した世界があると感じさせ、鑑賞者をその中に没入させていく。没入することによって、徐々にそのメディアの形式が見えなくなっていくのである。こういった経験はおそらく多くの人にとっても身に覚えがあるだろう。 没入という経験を通じて感じることができるように、媒体という概念それ自体は過去から現在、あちらからこちらに何かを記録し移動させるための「透明で空っぽな箱」のことであることが望まれる。箱がその中にあるひとつの世界を阻害しないものであることが望まれ、さらにその内容として何を入れるかは問われないことが理想的なメディアの考え方としてある。
しかしその一方で、メディアによる技術的な制限によって記録内容が変化することは避けられず、当然現実世界において「透明で空っぽな箱」であることはあり得ない。要は印画紙に映る母親の像のフレームの外側に何があったのかはわからないし、映画のショットの前後や、録音の環境の外側など、記録されていない無数の要素から、ほんの一部が選ばれ、残されたという事実がある。いずれのメディアも光や振動などの現象を断片的に切り取って媒介するに留まるのである。
さて、このように媒介の不完全性を抱えながら文化を構築してゆく各メディアの特性は、写真理論、映画理論、音響理論といった各メディアの歴史や理論を形成していく。
例えば芸術作品の中で実験的に展開されるメディア特性の現前として、20世紀アメリカの抽象絵画に代表されるモダニズムは、それぞれのメディア固有の特性(メディウム・スペシフィシティ)の探求を行い、この探究の形式は他の芸術作品にも影響を与えていった。音楽の事例を挙げるならばジョン・ケージの《4分33秒》はその極地にあるだろう。これらは絵画、音楽の「内容」にあたる部分を最小限に縮減し、「形式」を最大化する傾向へと発展することとなった。
また、芸術の範疇から外れるマスメディアなどの分野においても、基本的には消費者目線としては「内容」重視の傾向はあるものの、研究に関していえばあるメディアの性質が、芸術や産業の発展においてどのような影響を及ぼし、文化として受容されていったのかという「形式」に対する問いは主要な検証事項である。例えば、テレビや新聞における報道やドラマ、記事といった、一見「内容」さえも、放送時間や編成による制限、モニターのサイズ、文字数制限、印刷技術の限界といった「形式」によって規定され、自由であるとは到底言えない。マーシャル・マクルーハンが唱えた「メディアはメッセージである」は、このことを言い切った至言であるといっていいだろう。
ときに我々がメディアから何かを受け取る時、一方にメディアそれ自体の特質の現前があり、もう一方には内容それ自体への没入といった事態も同時に起こっていく。この二つの極のスペクトラムを行き来しながら、必要なメッセージを受け取ろうと試みていくのである。つまりメディアを通じた受容のプロセスは、頭の中に流れ込んでくるような受動的態度ではなく、積極的な読み取りの技術を使わなければならないのだ。そしてどのような技術と使い、受容を行なっていくかを再帰的に認識することは、簡単に言えばリテラシーであり、メディアの箱の形や色を確かめる術となる。
少し話は戻るが、この透明なメディアの姿形を探る営みとしてのメディア研究において、二項対立に亀裂を入れる重要なキーワードとして「断片性」が挙げられる。ジョルジュ=ディディ・ユベルマン『イメージそれでもなお』において、アウシュビッツの強制収容所でゾンダーコマンド(収容されたユダヤ人の中の労働部隊)によって撮影された4枚の写真に関する議論である。ホロコーストにおいてユダヤ人側から記録された唯一の写真として示される不明瞭な断片。これらは一方では「この写真こそが人類史上の災厄の本質である」と物神主義的に崇められ、もう一方では「こんなかすかなイメージは何も語りはしない」と証拠としての地位を退けられてきた。それに対して、この唯一の証拠写真の持つ意味について、ユベルマンが提示する答えは「断片として受け入れ、読み込みうる限りの分析を行う」ことであった。
この対照的な事例からも分かるように、メディアが提示する世界に接する時、人はしばしばそこに一つの完結した世界があると信じようとし、またあるいは何も読み取ろうとしない態度を取りもする。その態度に対するユベルマンの提示は誠に素朴で至高の境地に思える。メディアが人を惑わす二元論から抜け出すための「断片」の概念。これに正対して向き合うことこそが、もうここには居ない誰かの希望を託されるに然るべき、メディアを受容する者のひとつの使命なのである。
しかし突然に、メディア受容は没入/再帰を超えて、遠いある記憶が誤作動のように接続されることもある。それは作者が手渡したものでも、鑑賞者が積極的に受け取れるものでもないものしれない。
ロラン・バルトは遺作『明るい部屋』において、前期キャリアから築き上げた記号論的分析を「前言取り消し」し、インデックス性(物理的な記号の結びつき)によって結び付けられた「いまここにある」と「かつてそこにあった」の関係性を問い直していく。写真というメディアを通して突如として目前に突きつけられる過去に出会うこと。バルトの場合亡くなった母親の幼少期の写真との出会いは、バルト自身が出会ったことがあるはずのない母親の像でありながら、自らの中にある母の本質との邂逅でもあった。このことの検証はメディアの客観的な理論を編むでもなく、狂想的な妄想を膨らますでもなく、写真というメディアによってもたらされる突き刺すようにやってくる意味の体系「プンクトゥム」へと到達していくのである。
あるメディアを通じて啓示的にやってくる何かは、「これは〇〇」であると規定しようとするやいなや、逃げていき、不安定な意味の体系の中で偶然的・一時的にまた異なる本質が立ち現れ、また逃れていく。写真メディアによってもたらされたそんな奇妙な経験をバルトは詳細に書き残すことを試みたと捉えることができる。彼にして言えばそれはそもそも「手に追えない」ものなのである。
写真の話に大いに偏ってしまったが、録音の音源や、映画のふとした瞬間においても突発的で思いがけないなにかが生まれることは多くの人が経験していることなのではないだろうか。むしろそのような不可視で制御困難かつ共有困難なものに出会うために、作者は媒体を通じてものを作るのかもしれないし、鑑賞者はそれを観ること・聴くことをやめられないのかもしれない。
▼参考文献
ジョルジュ・ディディ=ユベルマン『イメージそれでもなお アウシュヴィッツからもぎ取られた四枚の写真』橋本一径訳、平凡社、2025年
マーシャル・マクルーハン『メディア論:人間の拡張の諸相』栗原裕、河本仲聖訳、みすず書房、1987年
ロラン・バルト『明るい部屋 写真についての覚書』花輪光訳、みすず書房、1997年
本文=舘かほる
注釈=玉田和平
舘かほる
写真研究者
1992年生まれ。自治体職員兼研究者。研究テーマは日本の初期人類学写真、北海道周辺の写真史。京都芸術大学非常勤講師。