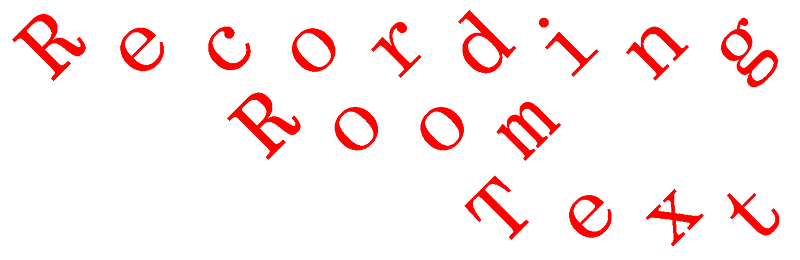サウンドスケープ
サウンドスケープとバーチャル空間の探索領域
tktk
3Dアーティスト/サウンドエンジニア
SNSを開くと異常気象によって四季の概念が崩れ夏と冬しかないとの嘆きがいくつも散見され、もはや定番ネタにすらなっている。たしかに温度だけでみればそうかもしれないが、音で季節の巡りを感じてみたらいいのにとふと思う。自宅の隣が小さな森で、ウグイスが鳴き始めると春の訪れを、鈴虫が鳴き始めるといよいよ秋めいてきたなと感じる。
音の知覚は耳だけの体験ではない。湿度や気圧によって音の響き方が変化することもあるが、冬の澄んだしんしんとした空気の張った感覚、肌触り、気配なども含めてクロスモーダルな感覚で音を捉えているはずだ。
音をさがしに散歩に出かけてみよう。たとえば足音ひとつとっても靴底の材質、床の材質、空間の構造、歩く人のクセや感情、年齢、聴く側との距離によって聴こえ方はまったく異なる。風に揺れる草木の音も、種類や風速・風向によって多彩な表情を見せてくれる。近くの海に足を運べば潮騒が聴こえてくる。これほど大きな面音源は他にないだろう。海を背にしてみれば聴こえ方がまったく変わる。頭の向き変えるだけで定位が変化し、プリミティブなインタラクティブミュージックになる。
このように周辺環境にある自然音や街の音を積極的に取り扱おうとする考え方が、1960年代末にカナダの作曲家マリー・シェーファーが提唱した「サウンドスケープ」である。ランドスケープ(景観)の-scapeにSoundを付けた造語で「音の風景」と訳される。「地球規模の自然界の音から、都市のざわめき、人工の音、記憶やイメージの中の音まで、我々を取り巻くありとあらゆる音を、一つの“風景”として捉える」という考え方だ。人々が音をどのように捉え、価値づけ/意味づけするのかを対象としている。
もともとランドスケープはある視点を選び取って空間を能動的に解釈するという意味がある。サウンドスケープはその視点を聴くことに置き換え、耳をすまして音に自覚的になることを目指している。そこには教育的な意義もある。
シェーファーは子ども向けに『Little Sound Education』というワークブックを執筆している。これはまずはじめに聴こえる音ぜんぶを紙に書き出してみることから始まる。紙に書き出すことで他人と比較可能になり、自分と他者の音の捉え方の違いを知って、聴くという行為がいかに主観的で個人的な体験であるかを学んでいく。そこからさらにリスニングウォークという音を聴く散歩を通して音の違いや環境へと意識を向けさせ、能動的に世界が開かれていくようになっている。
サウンドスケープの研究は1970年代に花開いた。しかし、概念が育まれた当時と現在とでは音の取り巻く状況が大きく異なる。とくにインターネットの登場とそれを取り巻くメディア環境の変化が大きい。シェーファーの研究ではラジオなどのメディアの取り扱いは大きくなく「分裂症的な音」として批判的に扱われていた。当時はまだメディアの環境化が今ほど進んでいなかったことと、サウンドスケープの思想が当時のエコロジー運動の影響を受けているのもあって進歩に対して距離を置く立場にあったことも背景にある。
しかし現代では、スマートフォンとノイズキャンセリング付きのイヤフォンによって外側と隔絶したパーソナルな空間を持ち歩きながら、インターネットを通じて常時他の世界と繋がっている。もはや環境そのもの分裂症的とさえ言えるだろう。
もともとサウンドスケープの発想は、伝統的な西洋音楽が音楽の対象を楽音に限定していることへの疑問から出発している。音楽はコンサートホールの中でのみ成立し、外側の自然音や日常音は排除されていた。しかし、いまや日常に音が溢れかえりここまで分裂症的な世界になると、もはやコンサートホールのような専用施設で音楽だけに集中できる時間のほうが希少で価値のあるものになってきた。
こうした変化や新しいメディアを含めて“環境”であり、その環境をとりまく音とどう向き合うかを考えることが現代において現実的なアプローチではないだろうか。スマートフォン以外にも当時にはなかったメディアのひとつがVRだ。筆者にとってはVR空間は制作と活動の場であり、もう一つの“環境”でもある。
VRは視界一面が覆われ空間内にいるという実存感が強く主観的な感覚が強いのが特徴である。動画などの他のメディアと比べても空間内にいて自らの意思で移動可能なため能動的な体験メディアと言っていいだろう。音についても頭部伝達関数(HRTF)による立体音響が標準で実装されており、頭の向きを変えると音の定位も変わる。音の複雑な反響や回折は再現できず簡略化された実装だが、それゆえに音の定位の変化が直接的で、インタラクティブに音の変化が自覚しやすい環境だ。サウンドスケープが能動的に音と向き合うことを重要視していることを考えるとこうしたVRの環境は相性がいい。
VRの制作側に立ってみるとノイズ含めて否応なく音が存在してしまう現実とは対照的に、VRでは空間に音を配置しないかぎり音が鳴ることはない。そのため、どんな音をどう置くのかを考える必要がある。ここに制作者が普段からどういうふうに音を捉えているかが制作物に如実に表れてくる。こうしたときに能動的に音を自覚していくサウンドスケープの発想が役に立ってくる。VRのの“Virtual”とは実質的、実体ではなくとも本質を示すという意味も含んでいる。VRであれ現実であれ観察し耳をすましその対象への本質と向き合うことからまず始まる。そうすることでより良い創作活動や生活環境が生まれるのではないだろうか。
シェーファーが楽音の世界から外の自然世界へと音楽の探索領域を広げたように、サウンドスケープの射程はVirtualの世界にも広がっていってほしい。
最後に音の観点からVRChatの中で印象深かったワールドを紹介する。ゲームが遊べるPCさえあれば体験できるのでぜひ楽しんでほしい。
カナディアン・ロッキーのようなランドスケープを再現した《Lost Valley Lake Retreat》は、作者のNProwler氏によると「VR内で自然を楽しむことで現実の自然の大切さにも目を向けてほしい」という意図を持って作られている。
《Namuanki》は前述のワールドとは対照的に現実にはない未知なる世界で、神秘的な巨大生物の咆哮、スピーカーと一体化した岩、サイケデリックな音を出す生物など、独創的なサウンドスケープが展開されている。
《Amebient》は滅びゆく世界でバケツやドラム缶に落ちる雨音で音遊びができるワールドだ。現実の雨漏りのバケツを見てこのワールドを思い出したり、空き缶で真似をしてみたくなるような広がりがあるのも優れた点だ。
《Fractone》VR内で音を合成するシンセサイザーとシーケンサーで音楽を作ることができる。実際に触ってみて音作りができる楽しさと、VRらしい立体的な音の配置ができる。
本文=tktk
注釈=玉田和平
tktk
3Dアーティスト/サウンドエンジニア
てけてけ。3Dアーティストとして活動する傍ら、VRのサウンドエンジニアリングも手がけている。きくおVRChat World『よるとうげ』、サンリオVfesパレード『SHOWBYROCK!! ましゅまいれっしゅ!! キセキかもしれないレゾナンス』など。また打楽器奏者として演奏も行う。