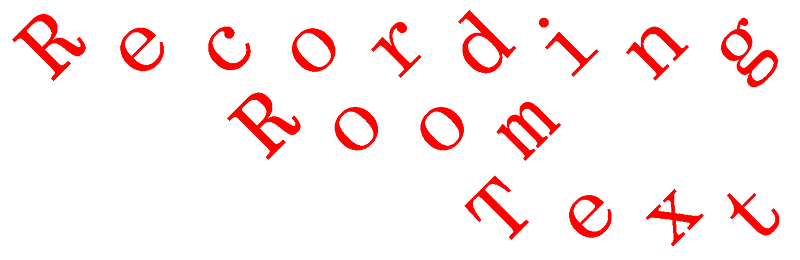再構成
音楽の再構成の文化と手法
角谷博栄
音楽プロデューサー/作曲家/編曲家
シティポップと渋谷系における再構成の美学
音楽における「再構成」という概念は、単なる引用やリミックスを超えて、過去の文脈やジャンル、スタイルを再編し、新たな意味や美的価値を与える行為として、20世紀後半以降の重要な創作原理となってきた。特に日本のポップスシーンにおいては、シティポップと渋谷系という二つの潮流が、独自の再構成的手法によって、音楽の地理的・文化的座標を揺さぶってきた代表に挙げられる。
1970年代後半から1980年代にかけて登場したシティポップは、AORやファンク、ソウルといった洋楽のスタイルを日本的感性で翻訳・融合したジャンルである。山下達郎や大瀧詠一といった音楽家たちは、当時の最新録音技術と高度な演奏力を駆使し、都市生活を彩るサウンドトラックとしての音楽を創り上げた。そこでは、西洋的でありながらも日本語の旋律や叙情性が混在し、「音楽的な意味の再構成」が精緻に行われていた。
興味深いのは、この再構成が短絡的な音楽的様式の模倣ではなく、日本の都市文化や消費社会と呼応する形で「都市の音」を創出した点である。シティポップにおける“夏”、“ドライブ”、“ネオン”、“海辺”といったイメージは、一般的な風景描写ではなく、音響的に演出された“都市の理想像”であり、それ自体が再構成された文化的記憶なのである。
それから約10年後、1990年代の渋谷系は、さらに新たな再構成の美学を提示した。ボサノバ、ノーザンソウル、フレンチポップ、映画音楽、エレクトロニカ──それらを縦横無尽に横断するサウンドは、まさにコラージュ的であり、ポストモダン的引用の美学に根ざしていた。フリッパーズ・ギターやピチカート・ファイヴ、小西康陽といったアーティストたちは、あえて元ネタの痕跡を残すことで、「知っている人だけが気づく」インターテキスチュアルな快楽を聴き手に提供した。
この時期の再構成は、一介のジャンルの融合ではなく、文化の地層を掘り起こし、それらを再編集して提示するキュレーター的な姿勢に近い。音楽はもはや創作の対象というよりも、編集・設計・文脈化の対象となりつつあった。まさに、渋谷系はプレイリスト的感性──断片をつなぎあわせ、そこに新たな風景を描くという行為──の先駆であり、現代のSpotify的リスニング体験と親和性が高いのはこのためである。
さらに、21世紀に入ってからは、こうした再構成的手法がグローバルなリスナーによって「再発見」され、逆輸入的に新たな価値を獲得する現象も見られる。シティポップがVaporwaveやFuture Funkといったジャンルの素材として使用されるようになったことは、再構成の再構成──つまり「再再構成」──という構造を浮かび上がらせる。
こうした再構成の系譜は、日本の音楽文化における「自己と他者」「伝統と模倣」「本物と複製」といった問題意識とも深く結びついている。例えば、シティポップにおける“西海岸の夢”は、実際のロサンゼルスやサンタモニカではなく、日本人が夢見る「理想化された外国」である。これは、文化的他者を模倣しつつ、独自の記号体系へと再統合する日本特有のスタイルでもある。
また、渋谷系の美学は、情報過多の時代における「選び取りの感性」とも言える。過去の無数の音楽、ビジュアル、カルチャーの断片を収集し、自らの文脈で編み直す行為は、まさに21世紀型の創作行為の先取りであり、現在のZ世代やAI生成文化における“再構成”の萌芽でもあった。情報を創造的に組み替える能力こそが、アーティストに求められる資質となった時代の、先駆的表現だったのである。
加えて、テクノロジーの発達も再構成の可能性を拡張させた。1980年代のマルチトラック録音技術、1990年代のサンプラーとMIDI機器、そして2000年代以降のDAW(Digital Audio Workstation)は、音楽制作における「編集」の重要性を飛躍的に高めた。これにより、音楽は「演奏」から「設計」へ、「録音」から「編集」へとパラダイムが移行していった。
現在、シティポップや渋谷系は、YouTubeやTikTok、Spotifyといったプラットフォームを通じて、世界中の若者たちの耳に届いている。だがそれは、いち一般のレトロな音楽の再流行ではない。むしろ、再構成という方法論、作品がデジタル時代に再解釈され、新たな形で更新され続けていることの証左である。
シティポップも渋谷系も、もはや、一つのジャンルではなく、方法論、ある時代精神を映す鏡である。そこには、音楽が“創られる”ものから“再編される”ものへと変容してきた過程が、明確に刻まれている。音楽の再構成とは、ただ音を並べ替えることではなく、記憶、文化、感性の地図を描き直す行為なのである。
こうした日本的な実践は、より広い時間軸と技術的変遷の中に位置づけることで、再構成という創作手法がいかにして生まれ、展開してきたのかを理解する手がかりとなる。
時代における再構成の手法と文化の変化
音楽における「再構成(reconstruction / recontextualization)」という発想は、決して最近になって登場したものではない。それはむしろ、20世紀の半ばから、私たちの耳に、そして音楽の定義そのものに問いを投げかけ続けてきた長い歴史をもっている。特に、録音技術の発展とともに、音楽は「演奏」や「作曲」といった従来の枠組みから解き放たれ、素材を拾い集め、再び編み直すという新たな創作の方法へと進化していった。
1940年代から現在に至るまでの音楽的再構成の流れをたどりながら、その時代ごとの技術や思想、そして文化的背景に焦点を当ててみたい。再構成はただの技法ではなく、音楽をめぐる認識や価値観を揺るがす問いそのものだったのである。
1. 1940年代〜1950年代:ミュージック・コンクレートの誕生
戦争が終わり、技術革新と社会的変革が同時進行で進んだ時代、音楽にもまた根本的な問い直しがなされた。ピエール・シェフェールによって提唱されたミュージック・コンクレートは、伝統的な楽器演奏を前提としない音楽のあり方を模索し、鉄道の音や工場の雑音、鳥のさえずりまでもが作品の素材として扱われるようになった。録音された音を切り貼りし、スピードやピッチを変化させることで生まれたこれらの音楽は、まさに「音の再配置」による芸術だった。そしてこれは、聴衆に対しても新たな聴覚の訓練を促すものとなった。音楽とは何か──その問いを技術によって突きつけた初めての瞬間だったと言える。
2. 1960年代〜1970年代:テープ音楽と実験電子音楽の深化
60年代から70年代にかけて、再構成の潮流は電子音楽の台頭とともにさらに深化する。シンセサイザーや初期のコンピュータ技術を取り入れた音楽家たちは、音響を科学的に操作することで、時間や空間における音の在り方を問い直した。シュトックハウゼンによる《Gesang der Jünglinge》はその代表例である。音楽はこの時代、ありふれた「旋律」や「リズム」の表現ではなく、音そのものが持つ質感や振る舞いに焦点を当てる芸術へとシフトしていった。ここでも再構成は、一介の手段ではなく、美学そのものへの問いとして機能していた。
3. 1980年代:サンプリング革命とヒップホップの台頭
80年代になると、再構成の手法はより民衆的なレベルへと浸透していく。都市のストリートで生まれたヒップホップは、過去の音楽を断片的に引用し、ループさせ、再文脈化することで、新たな物語を紡いだ。Public EnemyやGrandmaster Flashといったアーティストたちは、サンプル素材を通じて社会的・政治的なメッセージを発信し、音楽を凡庸な娯楽の域から押し広げた。再構成はここで、文化的引用の手段となり、オリジナリティの定義そのものを揺るがす議論を呼んだ。
4. 1990年代:デジタル編集の成熟とリミックス文化の拡大
90年代から2000年代にかけて、デジタル技術の発展により、音楽の再構成はより精緻で複雑なものになっていく。DAWの登場により、音の切断・配置・加工はもはや専門家の専売特許ではなくなった。Aphex TwinやDJ Shadowのようなアーティストたちは、過去の録音や断片的素材を再構成することで、新たな音響の地平を切り開いた。音楽は「完成された作品」という概念を脱し、オープンで流動的な存在へと変化していったのである。
5. 2000年代:インターネット時代とオープンカルチャーの拡大
ネットの普及は、音楽の再構成における最大の民主化をもたらした。誰もが素材にアクセスでき、誰もが創作者になれる。Girl TalkやDanger Mouseのように、著名な楽曲を大胆に再構成するアーティストが登場し、リスナーはその引用性とユーモアを楽しむようになった。また、クリエイティブ・コモンズなどの登場により、著作権の枠組みさえも問い直され、協働と共有を前提とした音楽文化が発展していく。
6. 2010年代〜2020年代:AIとアーカイブ再生産、ポスト自動生成時代
そして現在。AIによる音楽生成技術の進歩により、「誰が作ったのか」という問い自体が揺らいでいる。JukeboxやDadabots、Suno AIなどのAIモデルは、過去の音楽を学習し、それを再構成することで、まるで人間が作ったかのような音楽を生み出している。人と機械の協働、アーカイブの復元、リアルタイムの音楽生成…ここに至って、再構成はもはや手段ではなく、創作そのものの根幹をなす哲学となっている。
音楽における再構成の歴史は、技術の進歩とともに、その方法を変えながらも一貫して、「音楽とは何か」「誰が音楽を作るのか」「聴くとはどういうことか」という根源的な問いを私たちに突きつけてきた。そこには、音を通して時代を見つめ、文化を翻訳し、人間の感性そのものを拡張しようとする意志が宿っている。再構成とは、音楽という芸術の可能性を、絶えず開き続ける営みなのだ。
再構成のこれから
かつて創作とは、無から新たな何かを生み出すことだと考えられてきた。しかし今、サンプリングやリミックス、AIによる生成も含め、既存の素材を新たな文脈で組み替える行為は、創作の新たな核になりつつある。AI技術の進展により、再構成は単なる引用や模倣ではなく、創造の手段として独立しはじめている。また、SNSやストリーミングの時代においては、リスナー自身も日常的に音を再構成し、意味を更新していく。音楽はもはや「作品」ではなく、「体験」として捉え直されているのだ。
これからの創作において重要なのは、どれだけ新しいものを作るかではなく、どれだけ豊かに再構成できるか、ということなのかもしれない。再構成は記憶と現在を結びつけ、創作をより開かれたものにしていく可能性を秘めている。
本文=角谷博栄
注釈=玉田和平
角谷博栄
音楽プロデューサー/作曲家/編曲家
ミュージシャン、作曲家、ギタリスト、プロデューサー。音楽ユニット「ウワノソラ」およびその別名義「ウワノソラ’67」のメンバーとして活動。