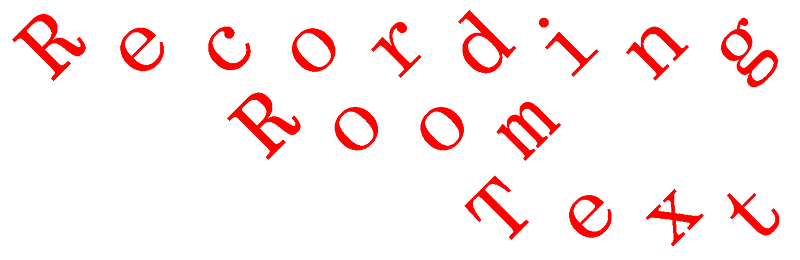録音
音を記録するということ
玉田和平
サウンドエンジニア/音楽家
普段私が録音をする時、ドラムセットやギターアンプなどの大音量が鳴る楽器に向かって躊躇いなくマイクを近づける。楽器によって音の鳴り方が違うので、それぞれの特性に見合うマイクや位置を選定する。完成する楽曲を想像しながらレコーダーを回す。ふと思う。普段こんな至近距離で楽器の音を聴くことなどないはずなのに、と。当たり前のようにマイクを近づける動作をきっかけに、今私が行っている録音という行為がどのようにして発展し、そしてその先に何があるのかを考えていこうと思う。
録音の起こりは1857年、江戸にハリスが来航した頃。パリのエドゥアール=レオン・スコット・ド・マルティンヴィルによってフォノートグラフという装置が開発された。これは音の振動を小さな針に伝えて紙に描画するというもので、記録された音を再生する機構はない。記録された図を元に音を視覚的に分析する用途で使われていた。世界最古の録音メディアだ。聴覚や振動でしか感じることのできなかった音という現象を視覚的に捉えることができるようになり、フォノートグラフは以後の録音技術の発展や音声学研究に大きな刺激と影響を与えた。
それから約20年後、1877年にトーマス・エジソンがフォノグラフを開発。こちらは再生することを念頭に設計されており、記録媒体が紙から金属の筒へと変化した。私たちが思う録音装置の原型となる。錫の箔が巻いてあるシリンダーに針で音の振動を伝え溝を削り込むことで記録する。ただし錫箔シリンダーは脆く、何度も繰り返し再生することはできず、また収録される帯域もかなり狭かった。とはいえ、この時初めて音が時間と空間を隔てて再生されたのだ。いままで音はその場限りの現象でしかなかったものが、1877年以降は再現可能なものとして変化した。この「時間と空間を隔てて再生される」という考え方は、1877年から今まで続く録音技術の大きな指標となっている。
1887年、エミール・ベルナリーによりグラモフォンが開発される。筒が円盤ディスクとなり、よく知られるレコードの形となる。1925年にはマイクロフォンの導入により、針の振動という物理的な記録方法から電気を使った録音へと変化していく。Western Electric社がマイク+増幅器+電気式カッティング装置の複合的な録音システムを開発し、より原音に忠実な記録が可能となっていく。この辺りから、録音技術は大衆に向けた商業に大きく関わり始めることになる。この高忠実度追求の思想は実に科学者的な目線で、何が何でも鳴った音を忠実に再現してやるという強い意思を感じる。この姿勢は、放送や映画音声、マスメディアなどでの信頼性確保などにも直結していると考えられる。
ここまでの歴史の中で特筆すべき点は、音は物理現象であるというところだ。物体が振動し、空気が振動することにより音が発生する。このように単純な現象であるにもかかわらず、なぜ人は音に興味を持ち、記録を残したいと考えたのだろうか。
音は多くの情報を伝達することのできる媒質だ。居場所を伝える、危険を伝える、喜びや悲しみなど感情を伝える伝達手段として使われてきた音という現象は、私たち人間の感情に何らかの作用をもたらすようになっている。録音技術の発展は単なる音の記録と再現ではなく、その先にある感情の変化の記録と再現であると言えるだろう。とても不安定な「感情の変化」という事象に科学者たちが夢中になり、それを残したり再現しようと研究を重ねているのは、そのこと自体が生物における音の重要性を指し示しているのではないだろうか。当時の録音スタジオは科学実験室の延長のような位置にあり、以後1960年代までは白衣を着た科学者たちがエンジニアリングを行っていたという。
話を戻して時代は1945年、第二次世界大戦の後。ドイツ国内で開発されていた磁気テープを用いた録音技術が連合軍により米国へ持ち帰られ、改良と実用化に向けた研究が行われた。私たちの知るカセットテープの原型となるものだ。磁気テープを用いた録音技術自体は1935年ごろには行われていたと言われているが、軍事用のプロパガンダなどに用いられていたこともあり、第二次世界大戦後まで一般公開は見送られていた。この磁気録音技術の導入により、今までの技術では物理的に不可能であった帯域の収録も可能となり、より原音に忠実な収録が可能となる。ここから録音技術は目まぐるしい進化を遂げ、また用途に合わせた細分化も進んでいく。これまでの例は全てモノラル録音の技術についてであったが、1949年に発表されたAmpex社のModel 300Aという2チャンネルに同時録音が可能な、いわゆるステレオ仕様のレコーダーが誕生した。このステレオ仕様の登場は録音技術において一つの大きなポイントとなっている。一度片耳を塞いだ状態で音を聴いてみていただきたい。片耳を閉じると、今まで感じていた空間的な奥行きが一気に失われ、距離感のない平坦な音が聴こえてくるだろう。音の前後感が希薄で、空間の響きも普段よりも強く聴こえ、普段とはまるで違う、ともすれば破綻したとも捉えられるような音として届くだろう。これは普段人間の耳が左右ふたつの入力からその差を感じ取り、脳内で立体的な音場として変換しているからだと言われている。故に片耳を閉じると変換が機能しなくなり、上記のような状態で聴こえてしまうのだ。実はこの片耳で聴いた状態は、1本のマイクロフォンに入力される音と限りなく近い。つまり私たちが聴いているような音を忠実に再現しようとするには、左右ふたつの入力が必要だということだ。このレコーダーの登場により、録音メディアの再現力はぐっと向上した。また、1957年には同一テープ状に2チャンネル以上の複数トラックを収録、オーバダビングをすることができるレコーダー、Model 3000をAmpex社が開発。この機種は音楽制作向けとして登場し、以降の音楽のあり方を大きく変えることとなる。
この辺りから、録音技術は単なる音の記録という領域から記録の編集・構築といった領域にまで裾野を広げていくことになる。今までは一つの時間軸上で録音したものが再現される、というのが常識であったものが、オーバーダビング手法の登場により、その時間軸にはなかった音を加えることができるようになったのだ。これにより音楽の表現の幅がぐっと広がり、現代私たちがよく聞く音楽の形とほぼ相違ない状態となった。大編成の楽曲を記録するのにも、演奏の技術さえあれば1人で構築することが可能となったのだ。この段階において音楽における録音は、単なる生演奏を保存するための技術ではなく、編集を経て音楽そのものを作る独自の表現手段として変化していった。そんな中で、エンジニアリングのあり方も変わっていくことになる。レコーダーや音にまつわる技術を扱うレコーディング・エンジニアと、音楽的な判断を行うプロデューサー/クリエイティブ・エンジニアが役割分担をして録音や音楽制作を行うようになった。複雑化する機器の操作を行うことと、その音楽が果たして良いものなのかを判断することはそもそもかなり離れた領域であり、各分野の専門がそこに従事することにより作品の質を担保するようになっていったのだ。これは現代の音楽プロダクションでもほぼ同じ状態で引き継がれている。冒頭の「大音量が鳴る楽器に向かって躊躇いなくマイクを近づける」という行為は、ここから発生している。編集行為を容易にするために、マイクロフォンを近づけて音を明瞭化していく。編集するためにはそれぞれの楽器の音が独立している方が良い。それらの音を組み合わせて編集し、2チャンネルのステレオ音源に落とし込むことで音楽を構築する。このような手法で制作された音楽がこの世には溢れており、私の心を動かした音楽もほとんどこの手法で作られたものである。故に先人たちを模倣し、私はこのようなマイキングを行っているのだ。
ふたたび話を戻し、1960年以降。Phillips社によるコンパクトカセットの開発による手軽な音楽メディアの普及や、Bell研究所やNHK技研によるPCM録音の開発によるデジタルデータ化などが進み、録音技術がより手軽に民衆の元に届くことになる。1991年にはPC上で起動するDAW(Digital Audio Workstation)が開発され、難解な機器操作や巨大なコンソールなどを置く必要がなくなっていき、コンパクトで高水準の録音スタジオの構築が可能となった。DAWの進化は目まぐるしく、特に2000年代に突入してからはあらゆるメーカーが独自のDAWソフトウェアを発表しており、価格も従来の録音機器に比べてかなりリーズナブルなものとなり個人で扱うことが可能となっていった。このようにして録音技術の民主化は行われていき、それに合わせて音楽の表現も拡張されていくこととなる。アナログ媒体時代では再現が不可能であった逆位相の収録や、信じられないほど高い音圧値の収録などが容易となり、既存の音楽のあり方では悪とされていた手法も、時代を経るごとに音楽の新たな進化の可能性として用いられることとなる。近年ではAmbisonics方式という立体的な音の収録技術が再注目されたりと、音楽のあり方の拡張が行われようとしている。
こういった録音技術の発展がある度に、人々は「何を再現し、何を創造するか」という点に立ち戻って議論を行うことになる。再現性と創造性、忠実性と操作性、技術における権威性と民主性など、あらゆる論点を軸に展開されている。もちろん結論がどちらかに傾くことはなく、張り詰めた緊張感を保ったまま録音技術は進化を続けている。
収録される音が向上していく一方で、音楽はどうだろうか。私は音楽を、音に何かを投影する営みだと捉えている。その投影が高純度・高効率で行われることと、音の情報が高密度であることは必ずしも比例関係にあるわけではない。投影とはすなわち音に含まれる音以外の情報を読み取ることであり、その行いこそが音を音楽たらしめる。そこには奏者や作曲者のエモーションがあり、人物や楽曲の背景や歴史があり、その大きな文脈と聴者の文脈の重なりによって評価が変動する。「何を再現し、何を創造するか」から展開される議論も、音以外の情報に重きをおいているからこそ保たれる天秤だ。どちらに優劣をつけるわけではなく、そのバランスを保った状態で作り出される音楽が幾層にも創造され、グラデーションが作られることが重要である。私にとっての録音技術とは、その投影の純度を上げ、人々のエモーションを刺激するために用いるツールである。エドゥアール=レオン・スコット・ド・マルティンヴィルが音を記録として残そうとしたのも、きっと彼自身が音あるいは音楽に感情を動かされた体験があるからなのではないか。
本文+注釈=玉田和平
玉田和平
サウンドエンジニア/音楽家
1991年生まれ。録音や楽曲ディレクション、自身の楽曲制作など。また「ANYO」のドラマーとして活動中。大阪芸術大学非常勤講師。