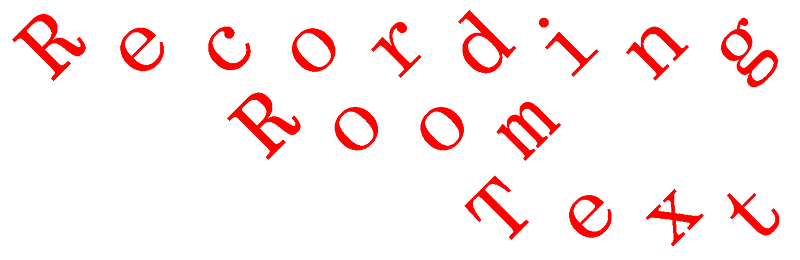アンサンブル
アンサンブルの社会的効能
舘かほる
写真研究者
「複数の要素をひとつに組み合わせる形式」がアンサンブルの最も簡易な説明である。例えばファッションであればトップスとボトムスのセットになった服から、統計力学における調査対象の集団まで、さまざまな文脈において利用される言葉である。こと音楽に関して言えば、合唱や合奏からオーケストラなど、複数の声や楽器から奏でられる音が組み合わせられながら、ひとつの音楽を奏でる形式がみられる。
アンサンブルは複数の音が重なることで、単音では得られない効果を生み出す。複数の音の重なりが生み出す効果は、それらの性質によって「ハーモニー」や「テクスチュア」、「形式」などの概念によって分類され、分析されてきた。ここで試みたいのは、アンサンブルが生み出す効果と社会空間における効能をアナロジカルに並列させて提示することである。
アンサンブルにおける効果の代表格である「ハーモニー」は、「コード(和音)/ディスコード(不協和音)」や「倍音」を扱い、調和に関する理論を主題とする。その語源は古代ギリシャの調和の神ハルモニアが由来であり、古くは音楽による調和は宇宙解明のヒントとしても考えられ、この世を成立させている絶対的真理へ至るためのモデルとして捉えられていた。
その後もローマ・カトリック教会におけるグレゴリウス聖歌による単旋律音楽(モノフォニー)から発展した中世の和声法などを基礎に、多声音楽が展開していったとされる。さらに当時のゴシック建築は天井が高く、音が響きやすい空間がその舞台となったことなどから、典礼音楽をより高尚なものに磨き上げていくために、ハーモニーの発展が促されたと考えられる。これらの要因からキリスト教音楽の発展においては、ハーモニーは唯一の神に捧げられる贈り物としての機能を持ち、人々と神を繋ぎ、救済へと導いていく契機となることから、「究極に高められた一点」への縦軸の志向をもっていると言えるだろう。
その一方で、高められた一点への志向は、典礼音楽を規律化し、純粋化を目指すものであったことから、包摂と排除のエコノミーが顕著に起こっていたことも特筆すべきポイントである。典礼音楽においては楽器を使用しないことや、女性の排除、世俗的な言語などがその対象となった。さらに社会的状況にこの排除のエコノミーを敷衍するならば、教義上の異端者に対する迫害や紛争、中世・近世に行われた魔女狩り、精神疾患罹患者に対する排除と崇拝、俗世との政治的対立など、現在もなお多くの宗教的・社会的問題の要因に関わっているといえるだろう。
このような「ハーモニー」に基づく調和のあり方に対し、複数の主旋律が横並びに並列されるアンサンブルの捉え方が「テクスチュア」である。テクスチュアは単旋律で構成される「モノフォニー」や、ゆるやかな主従を伴う「ヘテロフォニー」、複数の独立した旋律が同時に演奏される「ポリフォニー」など、旋律線の組み合わせに着目する観点から捉えるものである。
このテクスチュアの観点からの分析が重要な意味を持つのが、民族音楽の分野である。例えば、インドネシア・バリ島で演奏されるガムランは、低音の主旋律のベースを元に、複数の打楽器によってより高い音の高速なリズムを同時に演奏することからヘテロフォニー的ポリフォニーとして、ガムラン独自のテクスチュアを形作っている。さらにガムランのリズムは「コテカン」という技法によって奇数拍・偶数拍を複数人によって分担することにより、一人では鳴らすことができない速度・複雑さを持つ音を演奏することを可能にしている。この同時に鳴らす並列した細かい音の響きは「ポリリズム」とも呼ばれ。楽曲全体を包み込む細かい網目のように作用し、ガムラン特有の音響効果を生み出している。
ガムランが演奏される地域のひとつ、バリ島はヒンドゥー教の信仰地域である。演奏時は音楽のみならず舞踊・演劇が行われる。そこでは様々な役割を持った俗物的なものも含む)神々の物語を演じていく。ガムランによって上演される神話は、ブラフマー、ヴィシュヌ、シヴァの三大神を描く叙事詩『マハーバーラタ』などが代表例として挙げられ、特に世界の保持神ヴィシュヌが関わる物語においては、世俗の倫理観な規範を示したりする役割がある。つまりこれらの音楽には現世のカオスの中でどう生き延びるのかを示す役割があるのである。このことからテクスチュアによって捉えられる「ポリフォニー」的世界は世俗や下界といった横軸のフィールドで人々の生き方を学ぶ契機として機能するとも考えられるだろう。
なお、現代社会において「ポリフォニー」的実践が際立った成果を挙げている分野が、精神医療の分野である。統合失調症などを患う人々とポリフォニー的対話を展開する治療法「オープン・ダイアローグ」では、医者、患者、家族などを含む多数の関係者が対等に、話しを聞き・話すのワークを行う。患者と医者という権力勾配が生じやすい状況で、ひとりひとりが調和せずとも独立したそれぞれの声をあげる水平的なポリフォニー的状況を作り出すことよって、急性期の治癒が見込めた事例などがあり、臨床においても成果が出始めている。
以上のことから、高められた一点へ向かう縦軸と、対等性・並列性を重視する横軸のモデルによって、アンサンブルのふたつの効果は対照的に示すことができるかもしれない。アンサンブルは音楽のみならず、複数の要素の組み合わせという普遍的な概念として捉え返すと、例えば一神教における高められた一点への理想の希求、もう一方では並列した世俗的な人間関係における規範の提示といった形で社会的効能があるものとして捉え理解できるのではないだろうか。そしてそれぞれのモデルが志す、生きることの困難とそれを乗り越えるための契機が示されていると言えるだろう。
▼参考文献
木村佳代ほか『ガムラン入門 インドネシアのジャワガムランと舞踊』スタイルノート、2023
佐々木しのぶ・佐々木悠『キリスト教音楽への招待 聖なる空間に響く音楽』教文館、2012年
藤井知昭ほか『民族音楽概論』東京書籍、1992年
マイケル・スピッツァー『音楽の人類史 発展と伝播の8億年の物語』原書房、2023年
皆川厚一「バリ島の音楽と儀礼」『インドネシア芸能への招待 音楽・舞踊・演劇の世界』東京堂出版、2010年、219-247頁
皆川厚一「インドネシア、バリ島のガムランにおける位相性の考察」『神田外語大学紀要』33、2021年、67-88頁
本文=舘かほる
注釈=玉田和平
舘かほる
写真研究者
1992年生まれ。自治体職員兼研究者。研究テーマは日本の初期人類学写真、北海道周辺の写真史。京都芸術大学非常勤講師。